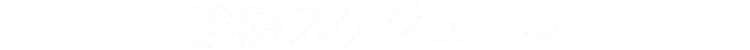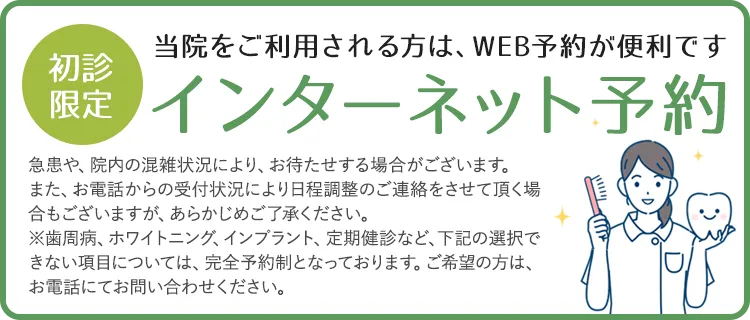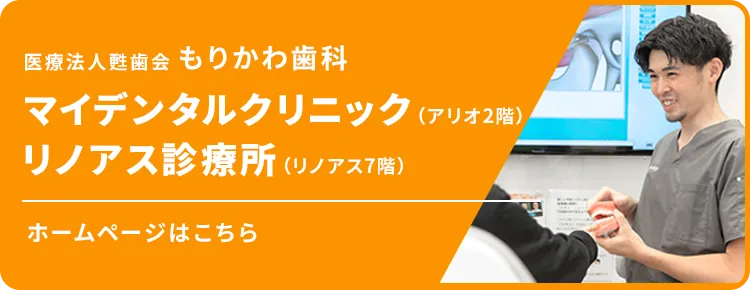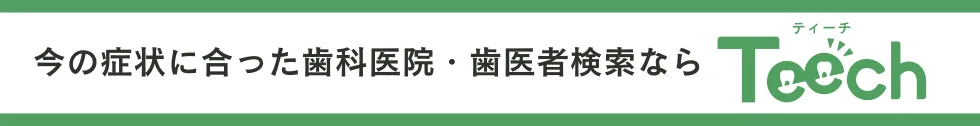こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。
ブリッジ治療とは、失った歯を補い、噛む機能や見た目を回復する治療法のひとつです。ブリッジ治療を検討されている方のなかには「ブリッジ治療のメリットは?」「費用はどれくらいなの?」などといった疑問をおもちの方もいるでしょう。
本記事では、ブリッジ治療のメリットやデメリット、治療の流れ、費用などについて詳しく解説します。現在、ブリッジ治療を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ブリッジ治療とは

ブリッジ治療とは、失った歯を補うための治療法の一つです。ブリッジ治療では、欠損した歯の両隣にある健康な歯を支えとして人工の歯を固定します。その見た目が橋のように見えることからブリッジと呼ばれています。
1本の歯を失った場合は、両隣の2本の歯を利用して3本つながったブリッジを作ります。固定式のため取り外しが不要で、入れ歯のような違和感が少ないのが特徴です。また、噛む感覚も自然に近いため、食事の際にもストレスを感じにくい治療法とされています。
ブリッジ治療のメリット

ブリッジ治療には、さまざまなメリットがあります。ここでは、ブリッジ治療のメリットについて解説します。
違和感が少ない
ブリッジ治療では、固定式の人工歯を使用するため、入れ歯のように取り外す必要がありません。そのため、噛む際の感覚が天然の歯に近く、ストレスを感じることなく食事を楽しめます。
治療期間が短い
ブリッジ治療は、一般的には数カ月以内に治療が終了する場合が多いです。忙しい生活のなかでも、手軽に治療を受けられる点がメリットです。
保険が適用される
ブリッジ治療は保険診療の範囲内で行えることが多く、費用を抑えることができます。選択する材料によっては自費診療になる場合もありますが、保険が適用される素材を選択すれば経済的負担を軽減できるでしょう。
見た目が自然
使用する素材によっては、天然歯に近い見た目を実現できます。特にセラミックなどの審美性の高い素材を選択すれば、周囲の歯と調和し、美しい仕上がりになります。見た目を重視する方にとっては大きなメリットといえるでしょう。
歯並びを維持できる
歯を失った状態で放置すると、周囲の歯が移動して歯並びが乱れることがあります。
しかし、ブリッジを装着することで周囲の歯を安定させ、歯並びを保つことができます。これにより、噛み合わせの乱れやさらに歯を失うリスクを軽減できるでしょう。
外科手術が不要
インプラント治療のような外科手術を伴わないため、体への負担が軽く、安心して治療を受けられます。治療自体もシンプルで、通院回数が少ない点も魅力の一つです。
ブリッジ治療のデメリット

ブリッジ治療にはいくつかのデメリットもあります。治療を受ける際には、以下の点についても十分に理解しておくことが重要です。
両隣の歯に負担がかかる
ブリッジは両隣の歯を支えとして固定されます。噛む力が支えとなる歯に集中するため、歯の寿命が縮まる可能性があります。特に支えとなる歯が弱っている場合には、将来的に問題が生じるリスクが高まるでしょう。
健康な歯を削る必要がある
ブリッジ治療では、人工歯を固定するために両隣の健康な歯を削らなければいけません。一度削った歯は元に戻せないため、健康な歯を削ることに抵抗がある方にとっては大きなデメリットといえるでしょう。
メンテナンスが難しい
ブリッジの場合、人工歯の下部や隣接する歯との境目に汚れが溜まりやすいです。しっかりとケアを行わないと虫歯や歯周病になるリスクが高まるでしょう。日常的にデンタルフロスやタフトブラシなどを使用してケアを行う必要があります。
適応とならない場合がある
ブリッジ治療の場合、失った歯の両隣に健康な歯があることが条件となります。そのため、歯を全て失っている場合には適応とならないのです。また、歯の状態や位置によっては、ほかの治療方法を検討しなければならない場合もあります。
ブリッジ治療の期間と通院頻度

ブリッジ治療にかかる期間は一般的に1〜2カ月程度で、通院頻度は平均3〜5回程度です。
ただし、虫歯や歯周病がある場合、それらの治療が優先されるため、全体の期間が延びる可能性があります。
ブリッジの平均寿命は約7〜8年とされていますが、適切にケアを行うことで10年以上使用できる場合もあります。寿命を左右する要因には、使用する素材や支台歯の健康状態、日々の口腔ケアの質が挙げられます。
特に、歯間ブラシやデンタルフロスを活用して汚れを丁寧に取り除くことが重要です。また、ブリッジを長く使用するためには、半年に1回程度の頻度で歯科検診を受けることが推奨されています。
ブリッジ治療の流れ

ブリッジ治療は、複数の工程を経て進められます。あらかじめ手順を理解しておくと安心です。以下では、ブリッジ治療の一般的な流れについて詳しく解説します。
問診と検査
まず、歯科医師による問診と口腔内の検査が行われます。この段階で、ブリッジ治療が適応となるか判断されます。また、治療方針や治療の流れについて説明を受けます。
支えとなる歯を削る
ブリッジを支えるために、両隣の歯(支台歯)を削ります。歯を削る際には、ブリッジが適切にフィットする形状に整えます。神経が残っている歯の場合は、痛みを軽減するために麻酔を使用することもあります。
型取り
削った歯をもとにブリッジを作製するため、歯型を取ります。専用の材料を使って、上下の噛み合わせも記録します。このときに仮歯を装着して治療中の見た目や噛む機能を一時的に補うこともあります。
ブリッジの作製
歯型をもとに、歯科技工士がブリッジを作製します。ブリッジの作製に使用する素材は保険診療か自費診療かで異なりますが、審美性や耐久性を考慮して選択されます。
試着と調整
完成したブリッジを試着し、口内でのフィット感や噛み合わせを確認します。この段階で違和感や不具合がある場合は、必要に応じて調整が行われます。
装着と固定
最終的な調整が完了したら、専用の接着剤を使ってブリッジを固定します。この後、歯科医師が噛み合わせや安定性を再確認し、問題がなければ治療は終了です。
ブリッジ治療にかかる費用

ブリッジ治療の費用は、保険診療と自費診療のどちらを選ぶかで大きく異なります。また、使用する素材や治療本数によっても変動します。以下では、それぞれの費用の目安について詳しく解説します。
保険診療の場合
保険診療のブリッジの場合、費用を抑えられるのが特徴です。
ただし、保険診療では使用できる素材が限られています。奥歯には銀色の金属が使用され、前歯には金属フレームに硬質レジン(樹脂)を貼り付けたものが使用されます。それぞれの費用は、以下のとおりです。
・奥歯の場合:1本あたり約3,000円〜5,000円
・前歯の場合:1本あたり約7,000円〜1万円
ブリッジは基本的に欠損した歯と両隣の歯の3本分を作るため、治療全体の費用は2万円~3万円程度になることが多いです。なお、この費用に検査や調整費用などが別途加算される場合があります。
自費診療の場合
自費診療を選ぶ場合、保険では使用できない高品質な素材を選べるのがメリットです。セラミックやジルコニアなどの素材は、見た目が天然歯に近く、審美性に優れています。また、金属を使用しない素材であれば金属アレルギーのリスクも回避できます。
ただし、全額自己負担になるため費用は高額です。費用の相場は、以下のとおりです。
・メタルボンド:1本あたり約8万円〜12万円
・オールセラミック:1本あたり約10万円〜16万円
・ジルコニア:1本あたり約10万円〜13万円
ブリッジは最低でも3本以上を必要とするため、治療全体では30万円以上になることが一般的です。
さらに、歯科医院や選ぶ素材によってはこれ以上の費用がかかる場合もあります。
ブリッジ治療を成功させるコツ

ブリッジ治療を成功させるポイントをまとめたので参考にしてみてください。
土台の歯が健康な状態か確認してもらう
ブリッジの支えとなる土台の歯が健康でなければ、治療後にトラブルが発生する可能性があります。土台となる歯が虫歯や歯周病になっていないかなどを事前にしっかり診断してもらうことが大切です。
無理のない設計になっているか確認する
ブリッジが無理のある設計になっていると、一部の歯に過剰な負担がかかり、破損や歯の痛みの原因になる可能性があります。そのため、噛み合わせや歯列に合わせた無理のない設計になっているかよく確認しましょう。
日々のケアを徹底する
ブリッジの寿命は、患者様自身のケアによって大きく変わります。人工歯と歯茎の間には汚れがたまりやすいため、歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスを活用して清潔な状態に保つことが大切です。特に、歯と歯茎の境目やブリッジの支台部分は注意して清掃しましょう。
定期的に歯科検診を受ける
ブリッジ治療後も、定期的に歯科検診を受けることでトラブルを未然に防げます。歯科医師がブリッジや支台の状態を確認し、必要に応じて調整やクリーニングを行うことで、ブリッジを長期間使用できるでしょう。
まとめ

ブリッジ治療とは、失った歯を補う治療法のひとつです。欠損した両隣の歯を支えにして橋を架けるように人工歯を装着します。ブリッジ治療には、メリットだけでなくデメリットもあるため、どちらも理解したうえで治療を受けるか検討することが重要です。
ブリッジ治療を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。