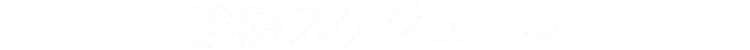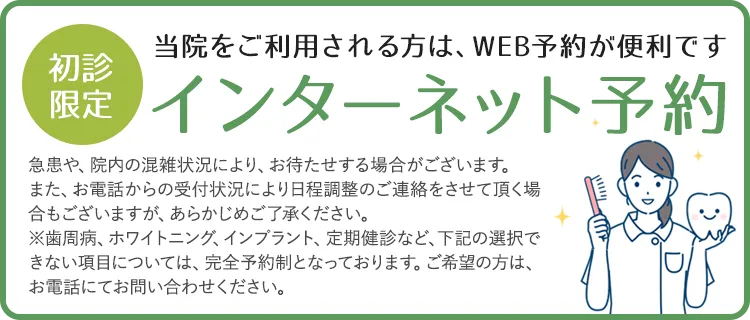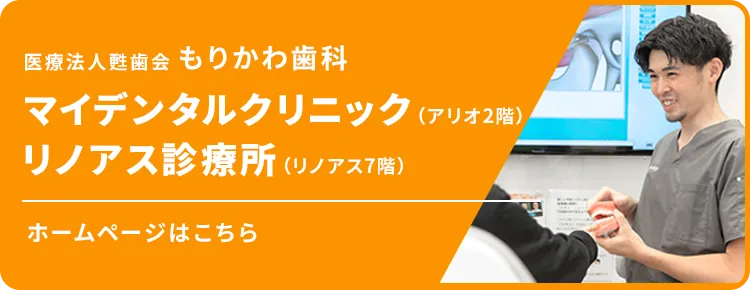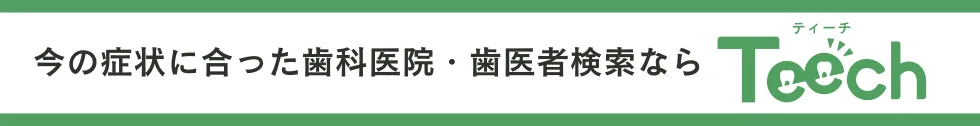こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。
子どもの歯並びが悪いと気づいていても「そのうち生え変わるから大丈夫」と考えて放置する方も少なくありません。
しかし、歯並びの乱れは見た目だけではなく、噛み合わせや発音、さらには全身の健康や成長発育にも影響を及ぼす可能性があります。また、子どものうちに適切な対応をしておくことで、将来的な矯正治療の負担を軽減できるケースもあります。
本記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やそれを放置した場合のリスク、矯正治療が必要なケースや予防法について詳しく解説していきます。お子さまの健やかな成長と笑顔を守るために、今できることを一緒に考えていきましょう。
目次
子どもの歯並びが悪くなる主な原因とは?

子どもの歯並びが悪くなる原因には、生活習慣や遺伝、口の使い方など、さまざまなものがあります。大人になってから矯正を始めると時間も費用もかかるため、できる限り子どものうちから原因を理解し、予防や早期対応を心がけることが大切です。
ここでは、歯並びの乱れにつながる主な要因について、日常生活に潜む小さなサインも含めて解説していきます。
遺伝的な要因
骨格や歯の大きさ、顎の形などは遺伝による影響が大きいとされています。例えば、顎が小さく歯が大きい場合、歯が並びきれずに重なったりねじれたりすることがあります。また、親の噛み合わせの特徴が子どもに遺伝することも多いです。
指しゃぶり・舌癖・口呼吸などの癖
3歳を過ぎても続く指しゃぶりや無意識に舌を前に押し出す癖(舌癖)、口を開けたままの呼吸(口呼吸)も、歯並びに悪影響を与える可能性があります。これらの習慣が長期間続くと、前歯が出っ張ったり、上下の歯が噛み合わなくなったりするなど、顎の成長バランスにも影響します。
食生活と噛む力の低下
現代の子どもはやわらかい食べ物を好む傾向があり、噛む回数が減少しています。噛むことで顎の骨が発達し、歯がきれいに並ぶためのスペースが確保されますが、噛む力が弱いと顎の成長が不十分になり、結果として歯並びが乱れやすくなります。
食生活の見直しは、歯並びにも大きく影響するのです。
乳歯の早期喪失や虫歯
乳歯が虫歯などで早く抜けると、後から生えてくる永久歯が正しい位置に並べなくなることがあります。乳歯には、永久歯が生えるための道しるべとしての役割があるため、歯並びを守る上では虫歯を予防することも重要なのです。
子どもの歯並びが悪いとどんなリスクがある?

「見た目がちょっと気になるだけ」と軽視されがちな子どもの歯並びの問題ですが、実は見た目以上にさまざまなリスクを生じます。噛み合わせの悪さは、口の機能だけではなく、発音や集中力、さらには全身のバランスや消化にも影響を及ぼす可能性があります。
小さなうちに起きた歪みが成長とともに拡大する可能性もあるため、歯並びの乱れを放置せず、早い段階でリスクを把握することが重要です。ここでは、子どもの歯並びが悪い場合に起こりうる主なリスクについて具体的に見ていきましょう。
発音や滑舌の問題が起こる
前歯にすき間があったり上下の歯が噛み合っていなかったりする場合、舌の位置が安定せず、サ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあります。歯並びは正しい発音の基礎となるため、歯の配置が乱れていると、滑舌に影響を及ぼすケースが多く見られます。
噛む力や消化機能の低下
噛み合わせが悪いと食べ物を十分に噛み切ることが難しくなり、丸飲みする傾向があります。その結果、胃腸に負担がかかり、消化不良や栄養吸収の効率低下を招くことがあります。
また、よく噛むことで顎の筋肉や骨が発達しますが、それが不十分だとさらなる歯並びの乱れにもつながります。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯並びが悪いと、歯と歯の間に汚れがたまりやすくなります。特に、歯ブラシの届きにくい部分が多くなることでプラーク(歯垢)が残りやすくなり、虫歯や歯肉炎などの原因になります。清掃性の悪さは、子どもの時期から口腔内の健康に大きな影響を与える要因のひとつです。
顔や体全体の歪みに発展する
歯並びや噛み合わせは、顔の筋肉や骨格、姿勢にも関連しています。例えば、片側ばかりで噛む癖があると左右の筋肉のバランスが崩れ、顎関節や首、肩にも負担がかかります。こうした影響が積み重なると、体の歪みや姿勢の乱れを引き起こすこともあるのです。
矯正したほうがよい子どもの歯並び

歯並びが多少悪くても、すべてのケースで矯正が必要というわけではありません。
しかし、中には早めに対処しないと将来の成長や噛み合わせ、さらには健康面に悪影響を与えるような歯並びの乱れもあります。専門的な判断が必要な場合も多いため、気になる場合は早めに歯科医の診断を受けることが大切です。
ここでは、特に矯正治療が検討されることの多い歯並びの例についてご紹介します。放置しておくと症状が進行する可能性があるため、早期発見・早期対応が重要です。
出っ歯(上顎前突)
出っ歯とは、上の前歯が前方に大きく突き出している状態です。転倒時に前歯をぶつけやすいというリスクもあります。また、唇が閉じにくくなるため口呼吸になりやすく、口内環境の悪化や感染症の原因となることもあります。
受け口(反対咬合)
受け口とは、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態です。放置すると顎の骨格が歪んで成長する恐れがあります。早期治療が推奨される代表的なケースのひとつで、発音や咀嚼、顎関節にも影響を与える可能性があります。
開咬(かいこう)
開咬とは、奥歯は噛み合っているのに、前歯が閉じきらずに上下にすき間がある状態です。指しゃぶりや舌癖が原因となることが多く、前歯で食べ物を噛み切れない、発音が不明瞭になるといった問題が出やすくなります。
叢生(そうせい)・ガタガタの歯
叢生とは、歯がきれいに並ばず、ねじれたり重なり合ったりしている状態です。歯が並ぶスペースが足りないことが原因で、清掃が行き届かず虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。見た目にも強く影響するため、思春期以降コンプレックスの原因となることもあります。
小児矯正は何歳ごろから?

「子どもの歯並びが気になるけれど、矯正を始めるタイミングがわからない」という保護者の方は多いでしょう。
実は、小児矯正には、早期に始めたほうがよいケースが存在します。適切な開始時期は歯並びの状態や成長発育の段階によって異なります。治療の効果を最大限に発揮するためには、タイミングを見極めることが大切です。
小児矯正は第1期治療と第2期治療に分かれています。第1期治療は、主に乳歯と永久歯が混在する6〜10歳頃に始められるもので、顎の成長バランスを整えるのが目的です。この段階で骨格のズレを改善することで、永久歯がきれいに並ぶスペースを確保できます。
第2期治療は、永久歯が生えそろう12歳前後から行うことが多く、歯の位置を細かく整えるのが主な目的です。
骨の柔らかい子どもの時期に治療を始めることで軽い負担で大きな改善が期待できます。気になる癖や歯並びの乱れがある場合は、5〜6歳頃から一度、歯科医院で相談してみるのがよいでしょう。
子どもの歯並びが悪くなるのを予防するためには

歯並びの乱れは矯正治療によって改善できますが、理想はそもそも歯並びが悪くならないよう予防することです。子どもは成長とともに歯や顎が変化していくため、日々の生活習慣や環境が歯並びに大きく影響を与えます。
つまり、保護者のちょっとした気づきや配慮によって、歯並びの乱れを未然に防ぐことが可能なのです。ここでは、家庭で実践できる予防法を中心に、歯並びを整えるために意識したいポイントを具体的にご紹介します。
よく噛む習慣を身につける
硬めの食材を取り入れ、しっかり噛む習慣を育てることで顎の骨や筋肉の発達を促進し、歯が並ぶためのスペースを確保しやすくなります。時間をかけて食べるよう促し、噛むことが良いことという意識づけを日常に取り入れていきましょう。
姿勢と呼吸を整える
猫背や口呼吸などの癖は、顎の成長バランスに影響を与え、歯並びを悪くする要因になります。正しい姿勢を意識し、口を閉じて鼻で呼吸する習慣を身につけることが大切です。特に、テレビやゲームなど、長時間の前傾姿勢には注意が必要です。
指しゃぶりや舌癖を早めに改善する
指しゃぶりや舌で前歯を押す癖(舌癖)は、歯に持続的な力をかけるため、前歯の突出や噛み合わせの異常を引き起こします。無理にやめさせるのではなく、子どもが安心できる環境を整えるとともに、必要に応じて小児歯科や保健師のサポートを活用することが重要です。
定期的に歯科検診を受ける
歯並びの乱れは、初期の段階では本人も気づきにくいものです。定期的に歯科検診を受けることで、異常の早期発見が可能になります。歯の生え変わりや顎の成長をチェックしてもらうことが、予防への第一歩です。
まとめ

子どもの歯並びが悪い状態を放置していると、発音や噛む力、口腔内の健康、さらには体のバランスや精神面にまで影響を及ぼす可能性があります。一見すると些細なズレでも、成長とともに問題が大きくなることもあるため、早めの対処が大切です。
遺伝だけではなく、日常の癖や生活習慣も歯並びに影響を与えます。このことを理解し、予防の視点を持つようにしましょう。大切なお子さまの健やかな成長を守るために、今できることから始めてみてください。
子どもの歯並びでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。