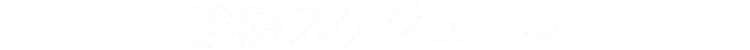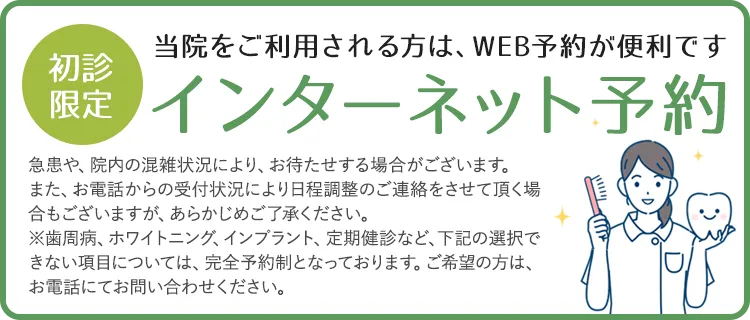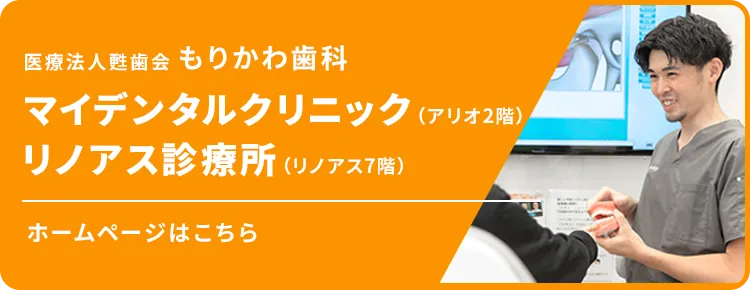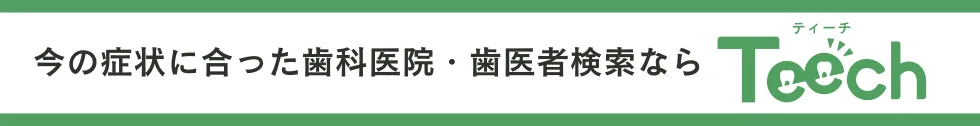こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。
子どもの歯並びについて、心配になる保護者の方は少なくありません。
特に、すきっ歯と呼ばれる歯と歯の間にすき間がある状態は、将来的な見た目や噛み合わせ、発音などに影響するのではないかと不安になるものです。成長の過程で自然に改善される場合もありますが、なかには早期の対処が必要となるケースもあります。
今回は、子どもがすきっ歯になる原因や放置するリスク、矯正の必要性などについて解説します。お子さんの歯並びにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
すきっ歯とは

すきっ歯とは、歯と歯の間にすき間がある状態のことで、専門用語では空隙歯列(くうげきしれつ)と呼ばれます。特に前歯の間にすき間がある場合、見た目の印象が大きく変わるため、多くの保護者の方が気にするポイントです。
子どもの場合、乳歯の段階ではすき間があるのが正常なことも多く、永久歯に生え変わるにつれて自然に閉じていくことがあります。
しかし、永久歯が生えそろってからもすき間が改善されない場合や、明らかな異常がある場合には、何らかの治療が必要になることもあるため注意が必要です。
子どもがすきっ歯になる主な原因

子どもがすきっ歯になる背景には、いくつかの原因が存在します。それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
乳歯と永久歯の大きさの違い
乳歯と永久歯は、見た目も機能も異なりますが、大きさにも明確な違いがあります。一般的に乳歯は永久歯よりも小さく、そのため乳歯の時期には歯と歯の間にすき間があるのが自然とされています。
このすき間は発育空隙とも呼ばれ、永久歯がスムーズに生えるために必要なスペースと考えられています。そのため、乳歯の段階で多少のすきっ歯が見られても、必ずしも異常とは限りません。
しかし、永久歯に生え変わったあともすき間が残るようであれば、歯の大きさや生え方に問題がある可能性も考えられます。
指しゃぶりや舌癖などの習慣
指しゃぶりや舌で前歯を押す癖は、歯並びや噛み合わせに影響を与えることがあります。
特に長期間にわたって指しゃぶりを続けていると、前歯が前方に押し出されてすきっ歯になる可能性があります。また、舌を前歯に押し当てる舌癖(ぜつへき)も、前歯のすき間を広げる要因になります。
これらの習慣は無意識のうちに行っていることが多く、保護者の方が早い段階で気づき、対応することが大切です。必要に応じて、小児歯科や小児矯正の歯科医師に相談することが望ましいでしょう。
虫歯による乳歯の喪失
乳歯は一時的なものと思われがちですが、永久歯が正しい位置に生えてくるための道しるべとして重要な役割を果たしています。
しかし、虫歯や歯ぐきの炎症によって乳歯が早い時期に抜けてしまうと、そのスペースを保てなくなり、周囲の歯が倒れ込んでくることがあります。これにより、あとから生えてくる永久歯の並びが乱れ、すきっ歯になる可能性があるのです。
特に前歯だけでなく奥歯でもこのような影響が起こるため、乳歯の段階でもしっかり歯磨きをして虫歯を防ぐことが大切です。定期的な歯科検診と日々の口腔ケアを通じて、乳歯の喪失を防ぐことがすきっ歯予防につながります。
歯の本数の異常
まれに、歯の本数が通常よりも少なかったり(先天性欠如歯)、逆に多かったり(過剰歯)する場合があります。こうした本数の異常があると、歯列のバランスが崩れ、すきっ歯の原因になります。
特に前歯の間に歯が埋まっていると、歯がきれいに並ばず、隙間ができることがあります。先天性欠如歯の場合には、そもそも永久歯が存在しないため、すき間が埋まらずに残ってしまいます。
レントゲン撮影などで歯の本数や位置を確認することが大切であり、必要に応じて矯正治療や抜歯などの処置が検討されます。
子どものすきっ歯を放置するリスク

すきっ歯が自然に治ることもありますが、放置することでさまざまな悪影響が出ることもあります。以下では、そのリスクについて具体的にご紹介します。
虫歯や歯周病になるリスクが高まる
すきっ歯の状態では、歯と歯の間に食べ物のカスや歯垢(プラーク)がたまりやすくなります。このすき間に汚れが残りやすくなることで、虫歯や歯ぐきの炎症、さらには歯周病へとつながる恐れがあります。
特に子どものうちは歯磨きがうまくできないことが多く、清掃不良が起こりやすいため注意が必要です。仕上げ磨きや定期的な歯科受診を通じて、口腔内を清潔な状態に保つことが大切です。
噛む力や発音に悪影響が出る
歯にすき間があると、上下の歯がしっかり噛み合わず、食べ物をうまく噛み切ったりすりつぶしたりする力が弱まることがあります。その結果、消化に負担がかかったり、食べることへの意欲が低下したりする場合もあります。
また、前歯にすき間があると発音時に空気が抜けやすくなり、サ行やタ行などの音が不明瞭になることがあります。これが原因で発音のクセがつき、コミュニケーションに影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。
見た目が気になるようになる
小さな子どもは見た目をそれほど気にしないことが多いですが、成長とともに外見に対する意識が高まっていきます。
特に小学校高学年から中学生になるころには、歯並びにコンプレックスを感じる子どもも増えてきます。すきっ歯が原因で人前で話すことを避けたり、笑顔を見せなくなったりすることがあれば、それは心理的なストレスのサインかもしれません。
見た目の問題は自尊心や人間関係にも関わってくるため、早めの対応が子どもの健やかな成長にとって重要です。
すきっ歯の矯正を検討したほうがよいケース

子どものすきっ歯に対して、すぐに矯正が必要というわけではありません。
しかし、すきっ歯の幅が広く、永久歯に生え変わってからも改善が見込めないと判断される場合は、矯正治療の対象となることがあります。また、噛み合わせに問題がある、発音や咀嚼に支障がある、心理的なストレスが大きいといった場合も治療を検討すべきです。
レントゲンなどによる診査を通じて、歯の位置やあごの成長バランスを総合的に評価してもらい、適切なタイミングで治療をはじめることが大切です。
すきっ歯を治す方法

子どものすきっ歯を治すための治療法は、年齢や歯の生え変わりの進み具合、あごの成長段階によって異なります。矯正治療は一般的に1期治療と2期治療に分かれており、それぞれに目的と方法があります。
1期治療
1期治療は、主に6歳から10歳ごろの乳歯と永久歯が混在している混合歯列期に行われる治療です。この時期は、あごの成長を促して永久歯が正しい位置に並ぶための土台を作ることを目的としています。
あごの発育に問題がある、指しゃぶりや舌癖などの悪習癖がある、歯列の幅が狭いなどの要因を早期に改善することで、自然と隙間が閉じることが期待できます。
使用される装置には、取り外し式の拡大床やマウスピース型の矯正装置などがあります。また、歯並びに影響を及ぼす癖を改善して口周りの筋肉を鍛えるMFTと呼ばれる治療が行われることもあります。
1期治療は、あごの成長を利用しながら無理のないかたちで歯並びの改善を目指す、大切なステップです。
2期治療
2期治療は、永久歯がすべて生えそろう12歳前後から行われる矯正治療で、歯を動かして最終的な歯並びや噛み合わせを整えることが主な目的です。すきっ歯が永久歯列期になっても改善されない場合には、この段階で本格的な矯正が検討されます。
一般的に、ワイヤー矯正やマウスピース矯正といった方法が用いられ、すき間をきれいに閉じることで、見た目の印象だけでなく、発音や噛み合わせの機能も整えられます。
必要に応じて1期治療から2期治療へと段階的に進めることで、より安定した仕上がりが期待できます。
まとめ

子どものすきっ歯は、成長とともに自然に治ることもありますが、原因によっては放置することでさまざまなリスクを招く可能性があります。見た目や発音、噛み合わせへの影響だけでなく、虫歯や歯周病のリスクが高まることもあるため注意が必要です。
早期に歯科医院で相談し、必要に応じて矯正治療を行うことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。子どもの健やかな口腔環境を守るためにも、日頃から歯の状態に目を配り、気になる点があれば早めに歯科医師に相談しましょう。
お子さんの歯並びにお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。