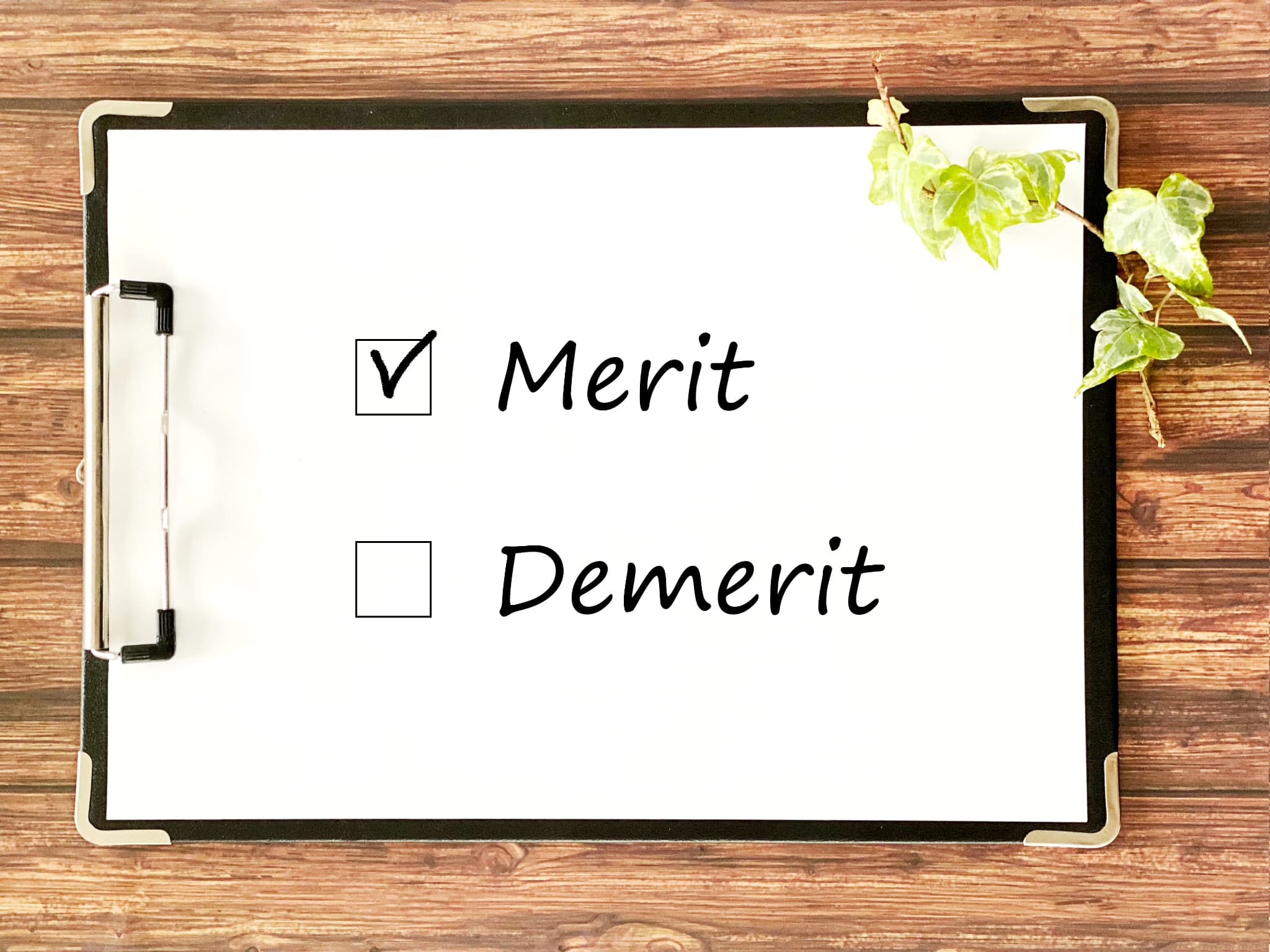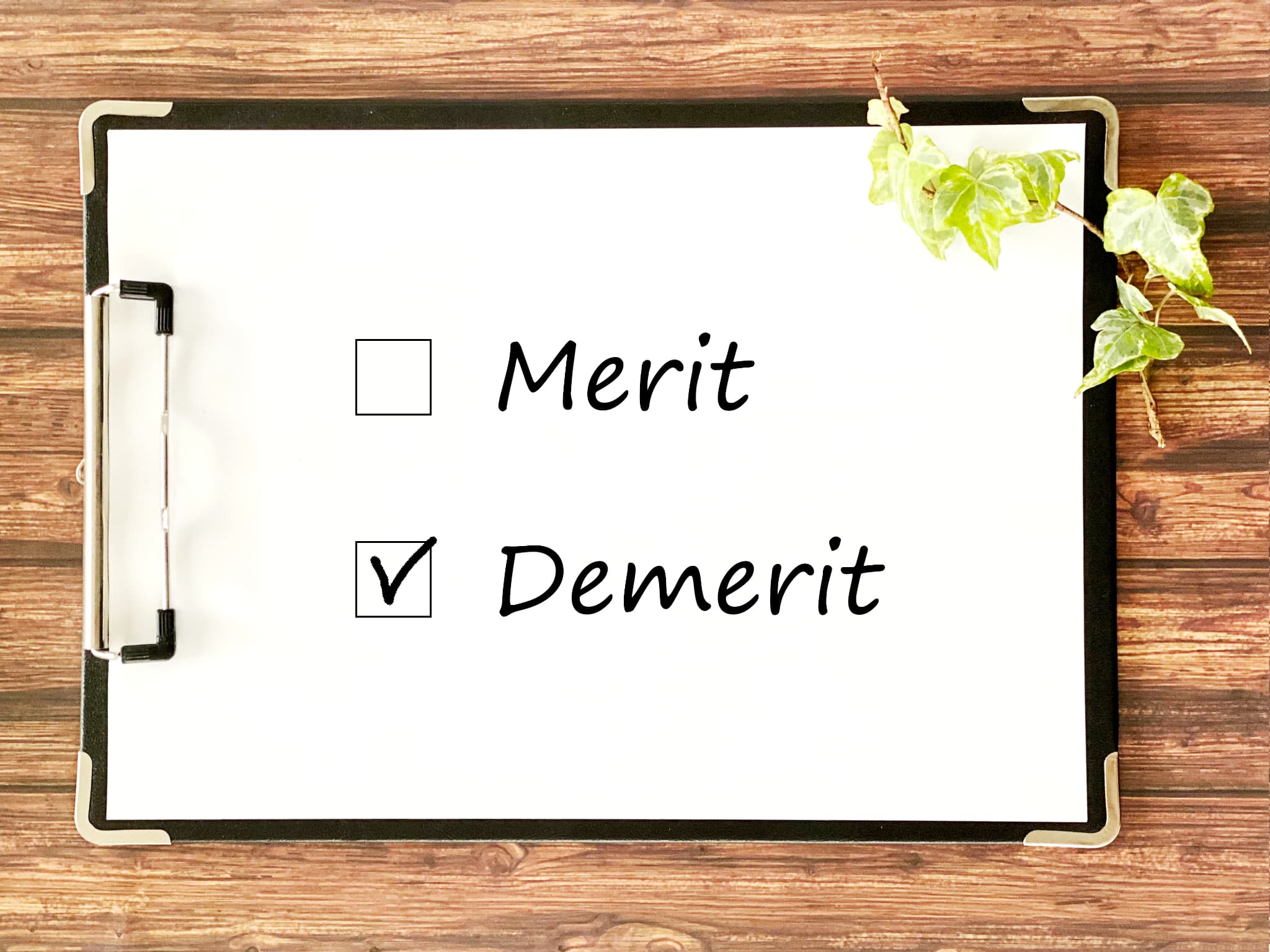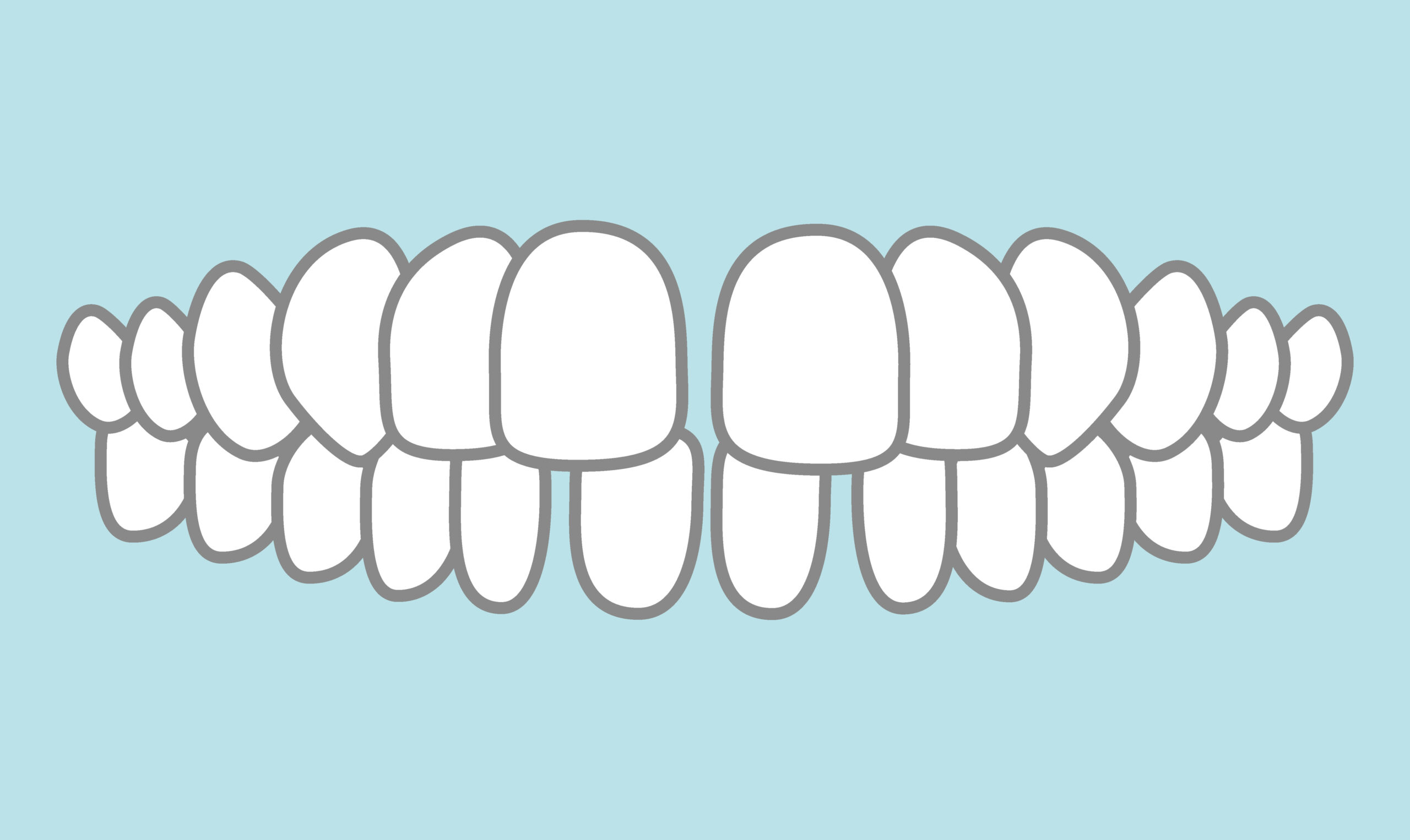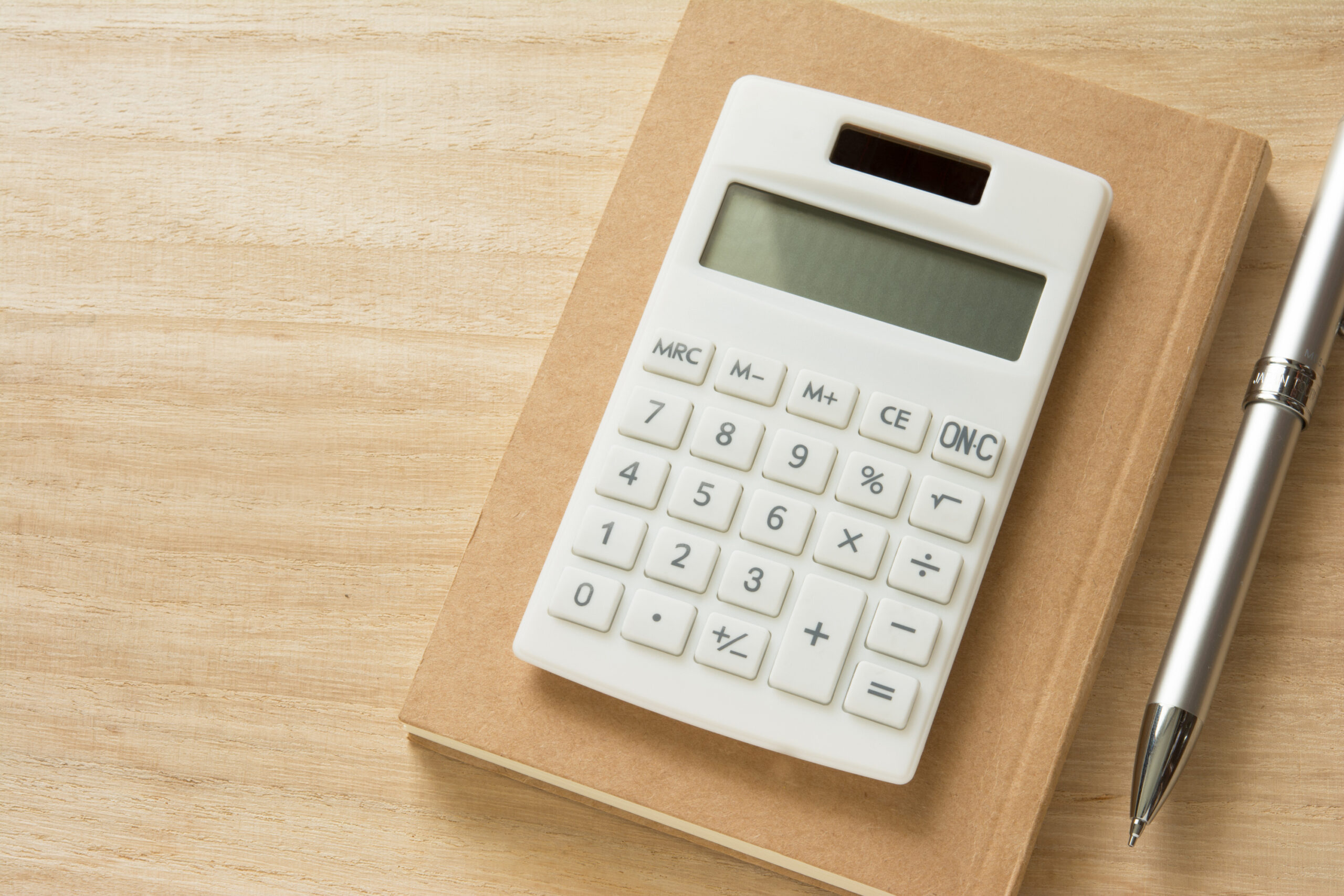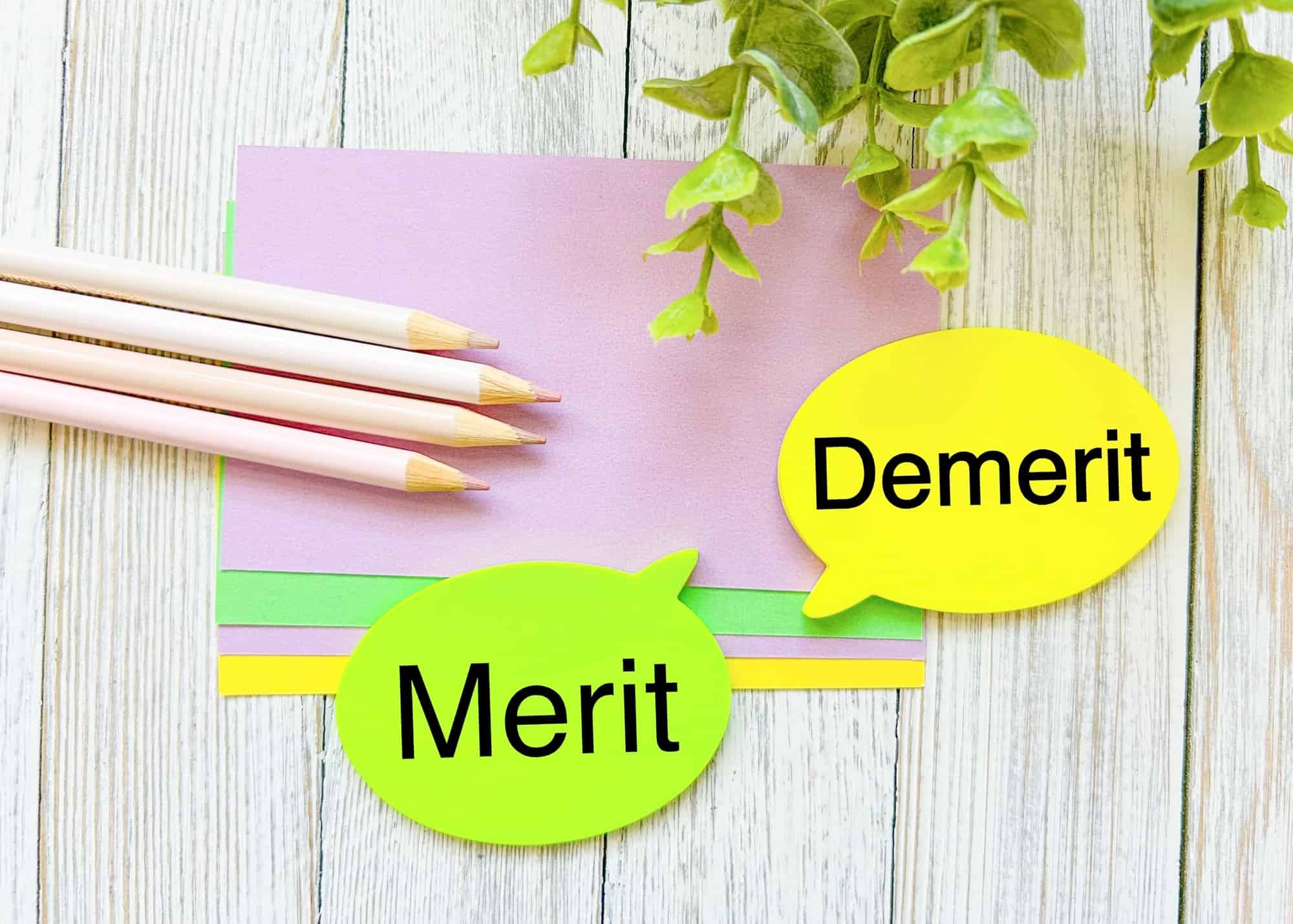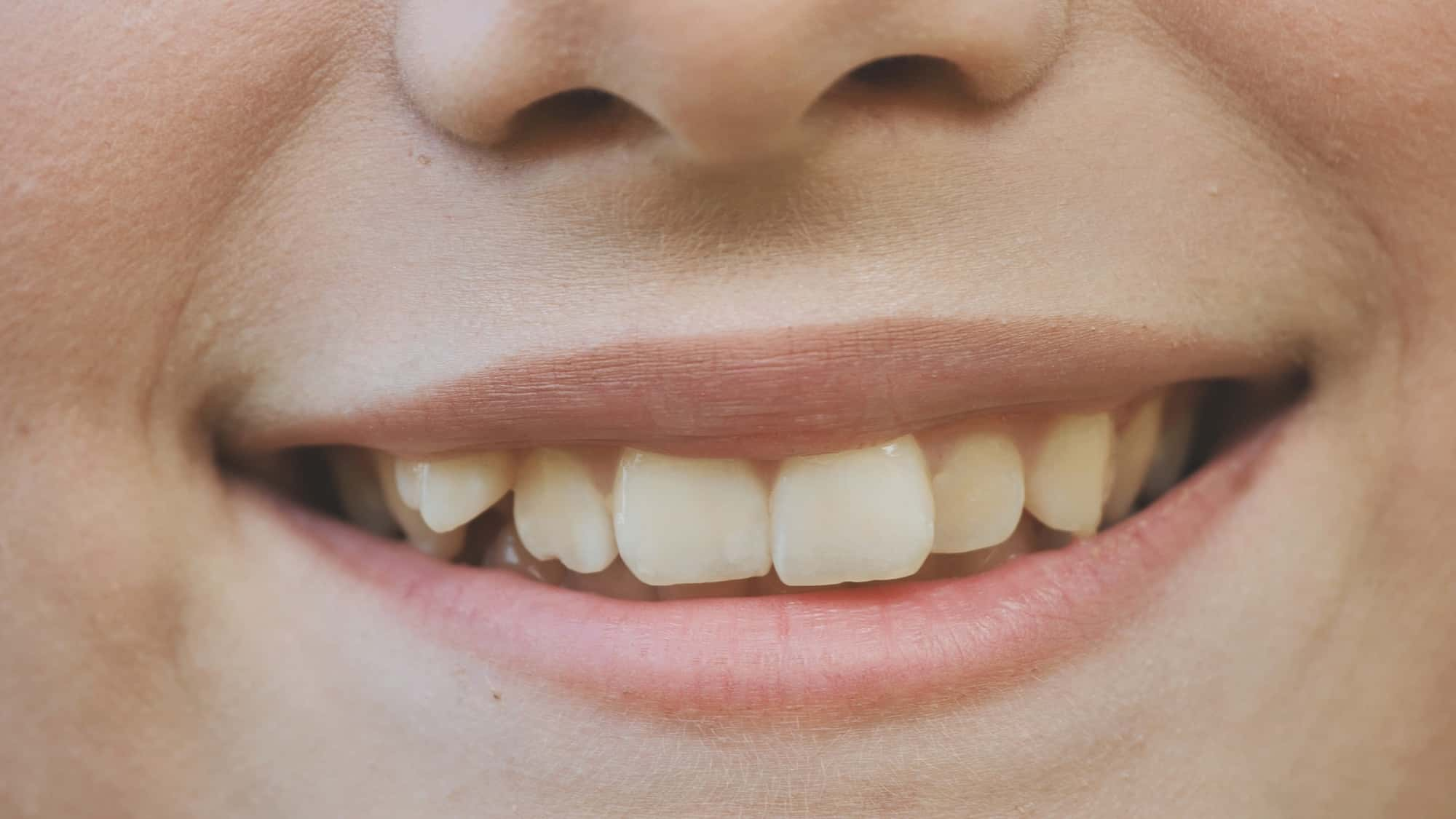こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。
ブリッジは、見た目や咀嚼機能を回復できる一方で、口臭が発生する原因となる可能性があることをご存じでしょうか。ご自身では気づかないことも多く、放置していると周囲に不快感を与えるおそれもあります。
今回は、ブリッジが口臭の原因になる理由や、口臭の原因がブリッジかどうか確認する方法、効果的な対処法などを詳しく解説します。
ブリッジとは

ブリッジとは、失った歯の機能を補う補綴(ほてつ)治療の1つで、欠損した歯の両隣の健康な歯を支台歯として、その間に人工歯を橋をかけるように固定する治療法です。連続した1〜3本程度の歯欠損に対して使用されることが多く、支台歯を削って被せ物(クラウン)を装着し、人工歯と連結させるように失った歯を補います。
取り外しが可能な入れ歯とは異なり、しっかりと固定されるため、咀嚼機能と審美性を自然に回復します。名称の由来は、歯間に橋を架ける構造から来ています。
ブリッジが口臭の原因になる理由

ブリッジが直接臭うわけではありませんが、その構造上、歯とブリッジの間や人工歯の下には汚れが溜まりやすく、そこで細菌が増殖することで口臭が発生します。特に、ブリッジの下は天然歯と違って歯ブラシが届きにくいため、清掃が不十分になりやすい場所です。長期間放置されたプラークや食べかすは、細菌の温床となり、強い臭いの元となるガスを発生させるのです。
さらに、プラークが蓄積されることで支台歯や歯茎に炎症が起きると、歯周病や虫歯を引き起こす原因にもなります。歯周病になると歯ぐきから膿が出て、より強い口臭の原因になることもあります。つまり、ブリッジはその構造上、意識してケアをしないと口臭が発生しやすいのです。
ただ歯を磨くだけではなく、デンタルフロスや歯間ブラシなどを活用して、人工歯の周辺や隙間まできちんと清掃を行うことが、ブリッジによる口臭を防ぐうえで非常に重要になります。
口臭の原因がブリッジかどうか確認する方法

口臭の原因がブリッジかどうかを正確に判断するには、まず日常的な口腔ケアを見直し、ほかに原因がないかを確認するのが基本です。鏡でブリッジ周辺の歯ぐきを観察し、赤みや腫れ、膿のような分泌が見られる場合は、そこが臭いの発生源である可能性が高いでしょう。
また、清掃直後の歯ブラシやフロスの臭いを嗅げば、独特の臭気を確認できることもあります。
歯科医院では、口臭測定器を使って臭いの数値や成分を測定し、客観的に知ることができます。加えて、歯科医師がブリッジを一時的に外して内部の状態を確認することで、隙間に汚れが詰まっていないか、歯ぐきが炎症を起こしていないかを詳しく調べてもらえます。
ブリッジが口臭の原因である場合の対処法

ブリッジが口臭の原因と判断された場合でも、適切な対処を行えば改善が見込めます。以下に、具体的な方法を紹介します。
自宅でできる対処法
まずは、ご自宅で行える対処法から確認しましょう。
丁寧に歯を磨く
ブリッジが原因の口臭を防ぐには、毎日の歯磨きを丁寧に行うことが大前提です。ブリッジのまわりは複雑な形状になっているため、通常の歯ブラシだけですべての汚れを取り除くことは非常に難しいです。特に、人工歯の下や支台歯との境目など、磨き残しが出やすい部分には注意が必要です。
歯磨きの際は、鏡を見ながら1本1本の歯を意識して磨き、特にブリッジの周辺は時間をかけて丁寧に磨いていくことが大切です。また、力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になるため、やさしく小刻みに動かすようにしましょう。
デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
ブリッジでは人工歯が連結しているため、通常のデンタルフロスを上から差し込むことができません。そのため、隙間に横から通せる歯間ブラシや、糸の先端が硬くなっている専用のスーパーフロスを活用しましょう。
歯と歯の間や歯ぐきとの境目にたまった汚れを除去することで、細菌の繁殖を防ぎ、口臭対策につながります。使い方に不安がある場合は、歯科医院で指導を受けるとよいでしょう。
マウスウォッシュなどの口臭ケアを行う
ブリッジからの口臭を抑えるための補助的な方法として、マウスウォッシュなどの口腔ケア製品を活用するのも有効です。マウスウォッシュを使うと、歯ブラシが届きにくいブリッジの細かい隙間にいる細菌も減少させることができます。
就寝前に使用すれば、寝ている間に増える口内細菌の活動を抑えることができ、朝の口臭や口のネバつきを予防する効果も期待できます。朝の歯磨き後に使用すれば、日中の口臭対策としても有効です。また、マウスウォッシュには口臭予防だけではなく、歯垢の付着抑制や歯周病予防、虫歯予防といったメリットもあります。
ただし、あくまで補助的なケアであり、毎日の歯磨きやフロスなどの基本的なケアを欠かさないことが大前提です。正しい使用方法を守りながら上手に活用しましょう。
臭いが強い食べ物を避ける
ニンニクやニラ、玉ねぎなどは、口臭を発生させる食材として有名です。これらは体内で分解される過程でも強い臭い成分を生成し、長時間にわたって口臭を強くします。ブリッジの清掃が行き届いていないと、その臭い成分が残留して、さらに悪化するケースもあります。
また、アルコール類も口内を乾燥させて細菌の増殖を助長することがあるため、注意が必要です。
歯科医院で行うケア
これまでは自宅でできる方法を紹介してきましたが、歯科医院で受けられる口臭ケアもあります。詳しく確認していきましょう。
ブリッジを作り直す
ブリッジが著しく劣化している場合や支台歯に大きな問題がある場合は、ブリッジを作り直す選択肢が現実的です。ブリッジを長く使い続けていると、接着面に隙間が生じたり変形したりして、細菌がたまりやすくなります。これによって口臭が慢性化することも少なくありません。
まず古いブリッジを丁寧に取り外し、支台歯の状態を確認します。虫歯や歯周病が進行している場合は、それらを治療して歯の土台を整えてから新しいブリッジを作ります。
また、作り直しの際には、保険診療と自費診療のどちらを選ぶかで、使える素材や精度が変わってきます。金属の影響による口臭が気になる場合は、オールセラミックやジルコニアといった、審美性・清掃性に優れた自費診療の素材を使用するのも1つの方法です。
自費診療のブリッジは費用は高くなる傾向がありますが、見た目が自然で、臭いも発生しにくいとされています。
ただし、すべてのケースで作り直しが必要というわけではありません。まずは現在のブリッジの状態を確認し、歯科医師と相談のうえで適切な方法を選択することが重要です。
インプラントに切り替える
口臭の原因がブリッジそのものや支台歯への負担に起因している場合、インプラントへの切り替えを検討するのも1つの手段です。インプラントは、周囲の健康な歯を削らずに済み、独立した人工歯根としてしっかり固定されるため、汚れが溜まりにくく、口臭の発生リスクを抑えることができます。
また、噛み心地や見た目も自然で、食事や会話のストレスが軽減されるのもメリットです。ブリッジの取り外しやインプラント埋入には一定の治療期間が必要ですが、将来的なトラブルを防ぐ長期的な視点での選択といえます。
定期的に検診やクリーニングを受ける
口臭の原因を根本から解消し、ブリッジを長持ちさせるためには、歯科医院での定期的な検診とプロによるクリーニングが欠かせません。自宅でのケアだけでは落としきれない細かな汚れや、歯ぐきの奥深くにたまった歯石などは、専門の器具を使って丁寧に取り除く必要があります。
3〜6か月ごとに歯科医院でチェックを受けることが大切です。定期検診では、ブリッジの適合状態や噛み合わせの調整も行われるため、知らないうちに起きていたズレや緩みを早期に発見できるというメリットもあります。
また、歯科医師や歯科衛生士による専門的な清掃(PMTCなど)を受けることで、通常の歯磨きでは落とせないバイオフィルム(細菌の膜)も除去できます。これにより、ブリッジの表面が滑らかに保たれ、汚れや細菌がつきにくい状態になります。
定期的なプロのケアを習慣にすることで、口臭のリスクを大幅に減らすと同時に、ブリッジ自体の寿命も延ばせます。
まとめ

ブリッジは構造上の理由から、口臭の原因になりうることがあります。特に、清掃が行き届いていないと、ブリッジの下や支台歯に汚れが溜まり、細菌が繁殖して不快な臭いを引き起こすこともあります。
口臭が気になる場合は、まず丁寧なブラッシングとデンタルフロスを使ったケアを徹底しましょう。必要に応じて歯科医院でのクリーニングやブリッジの作り直しやインプラントへの切り替えを検討することが大切です。
気になる症状がある場合は、早めに歯科医師に相談し、適切な対処を行いましょう。
ブリッジや口臭でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療、インプラント、セラミック治療、ホワイトニング、歯科矯正など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。