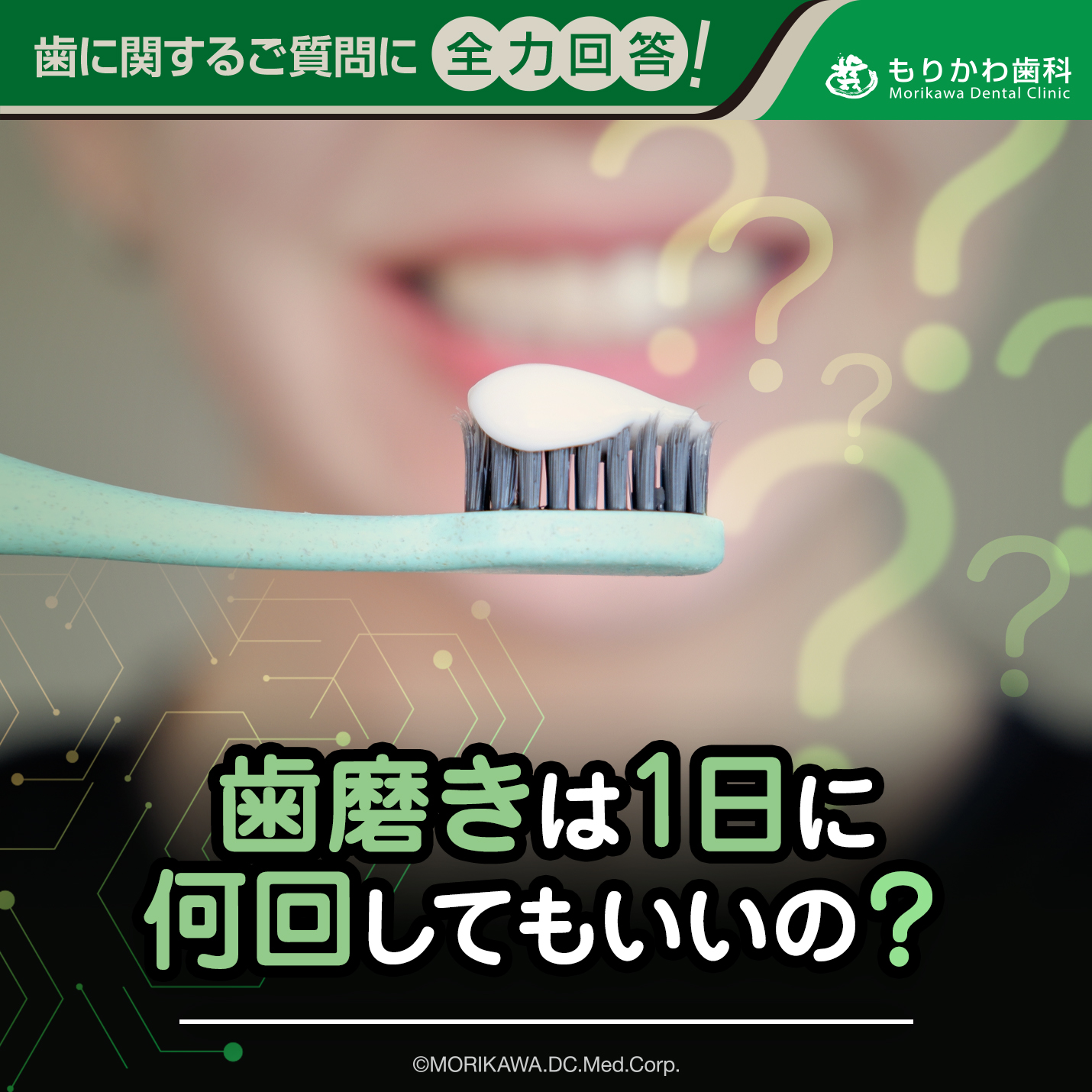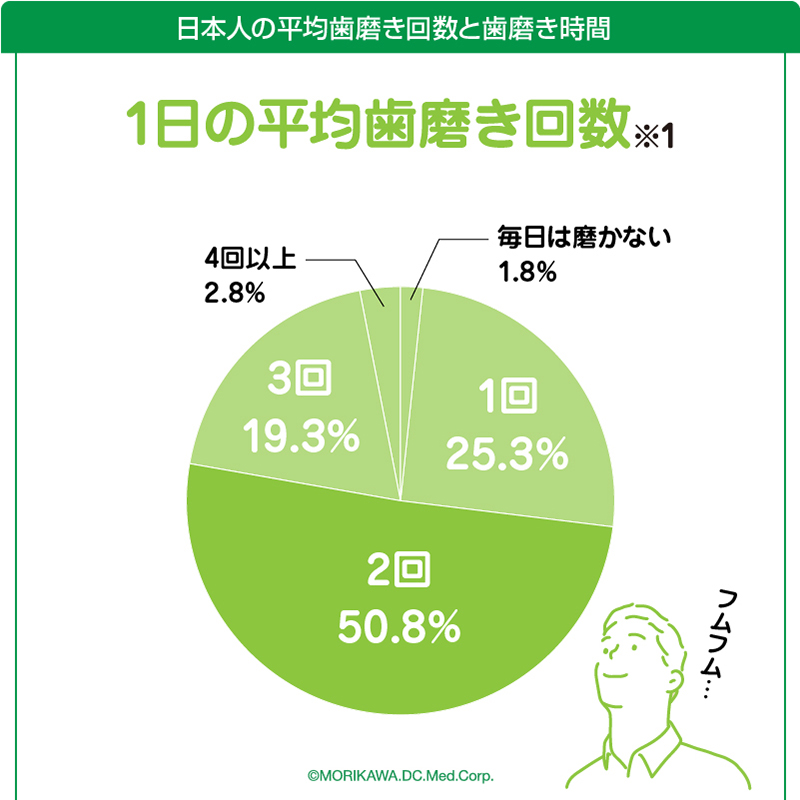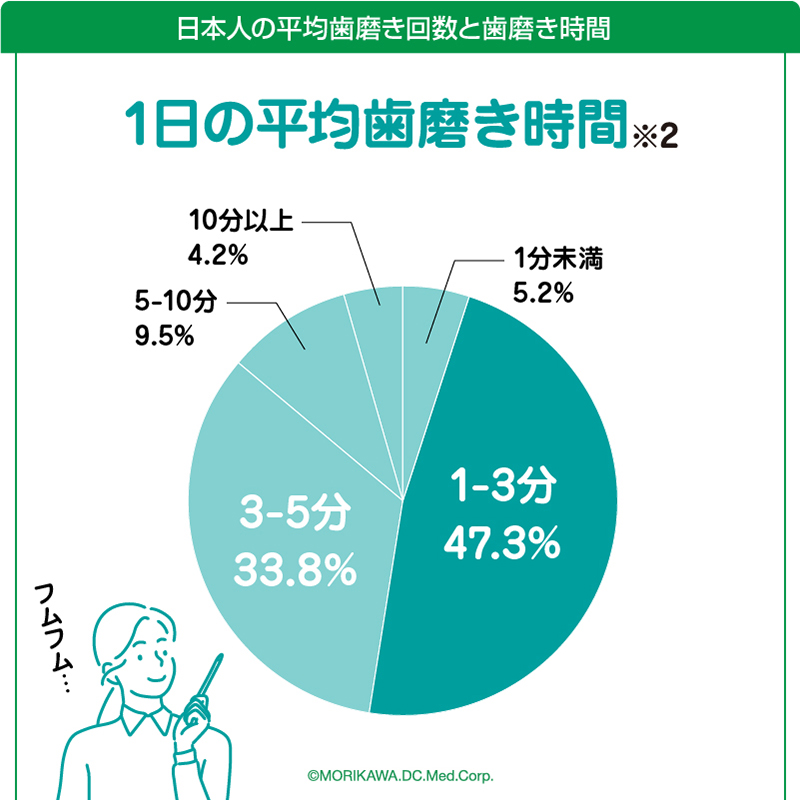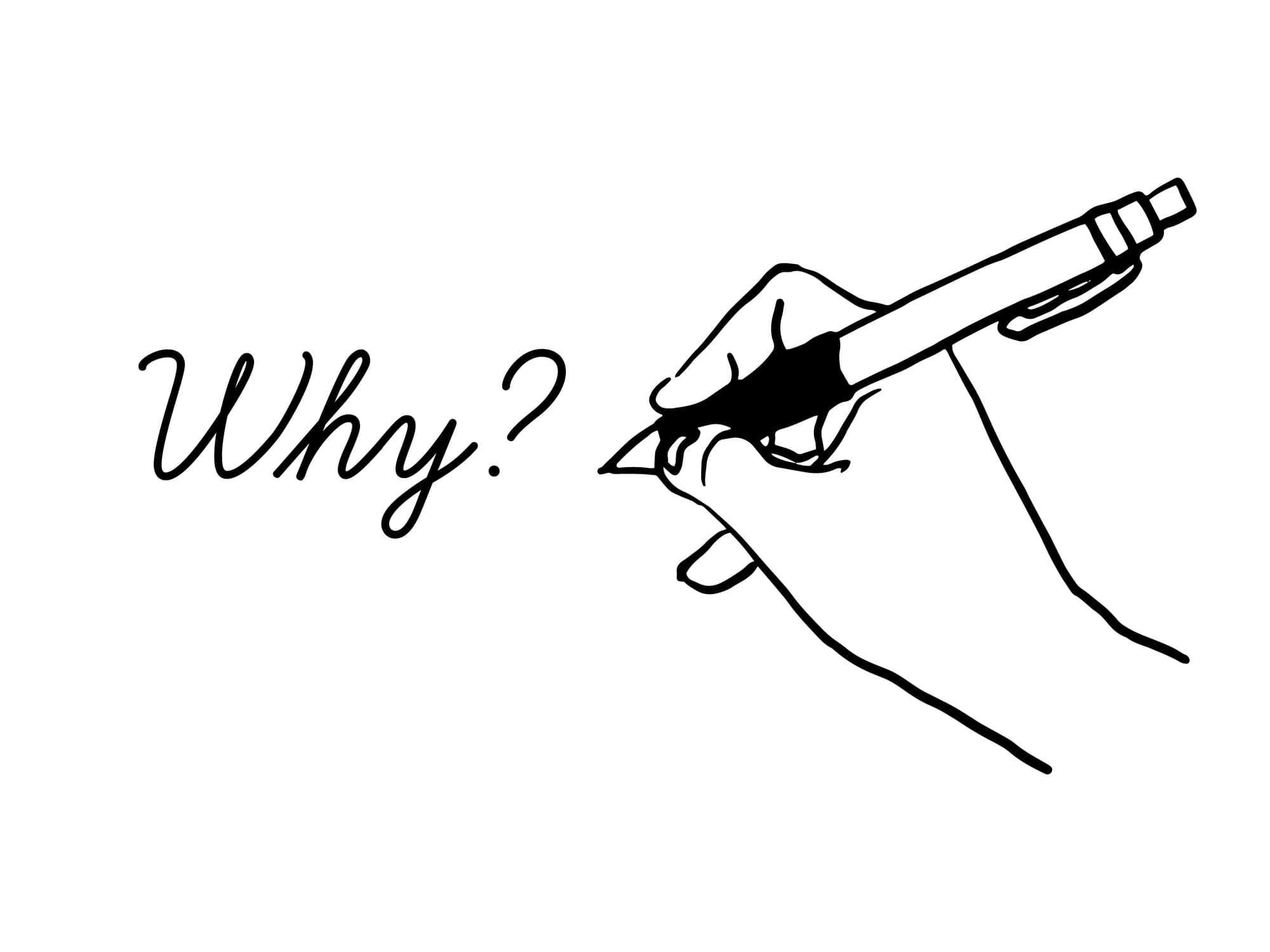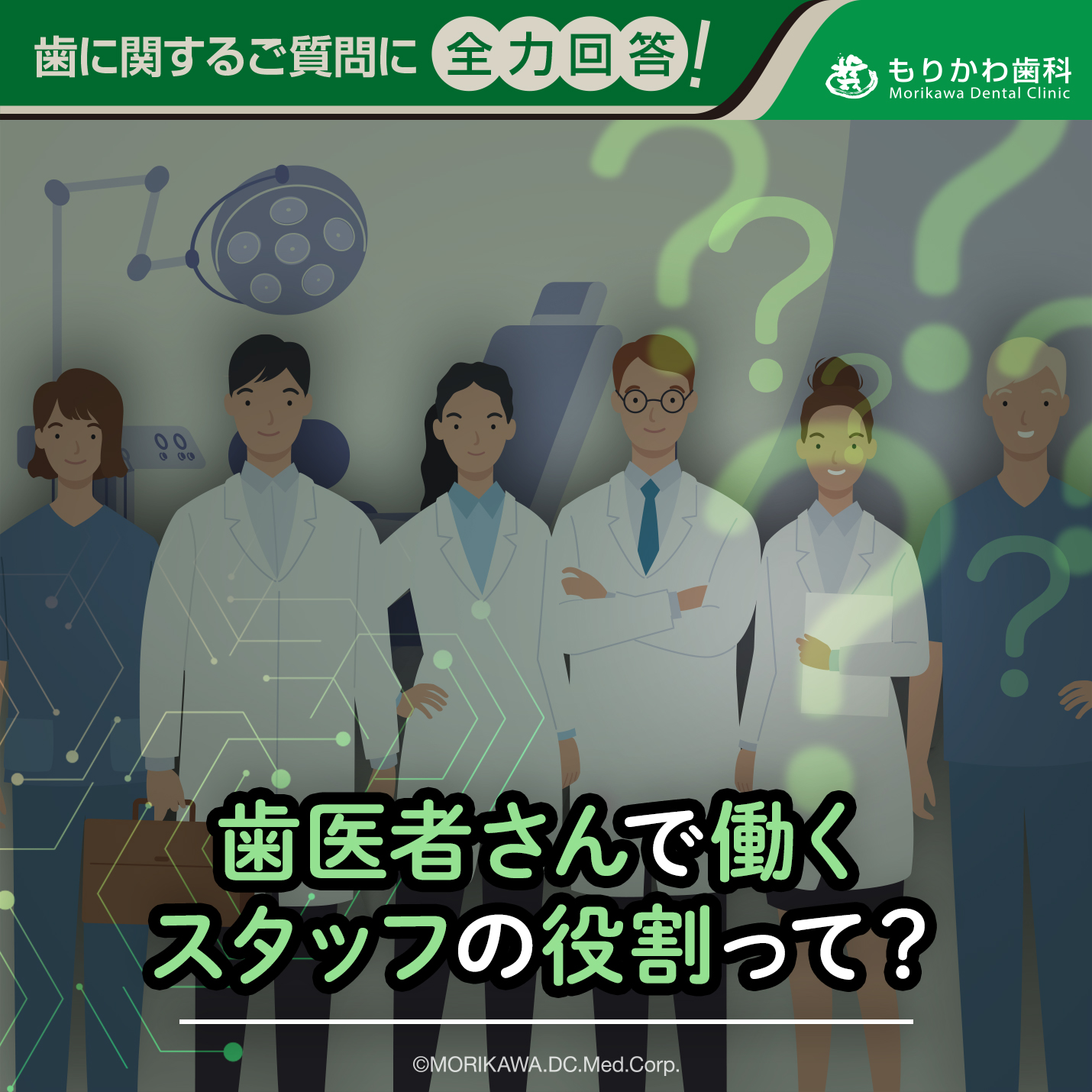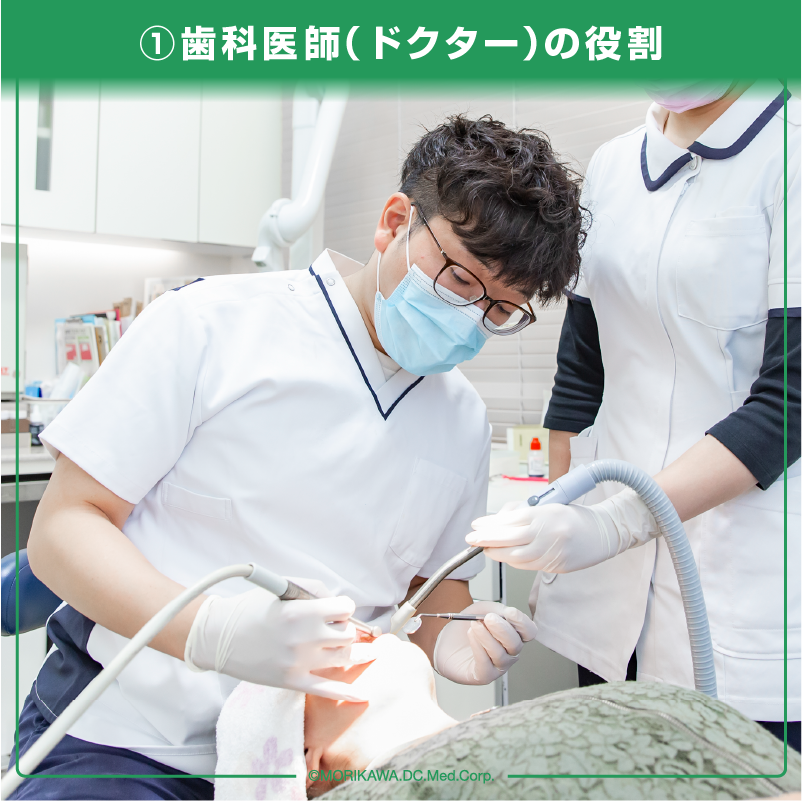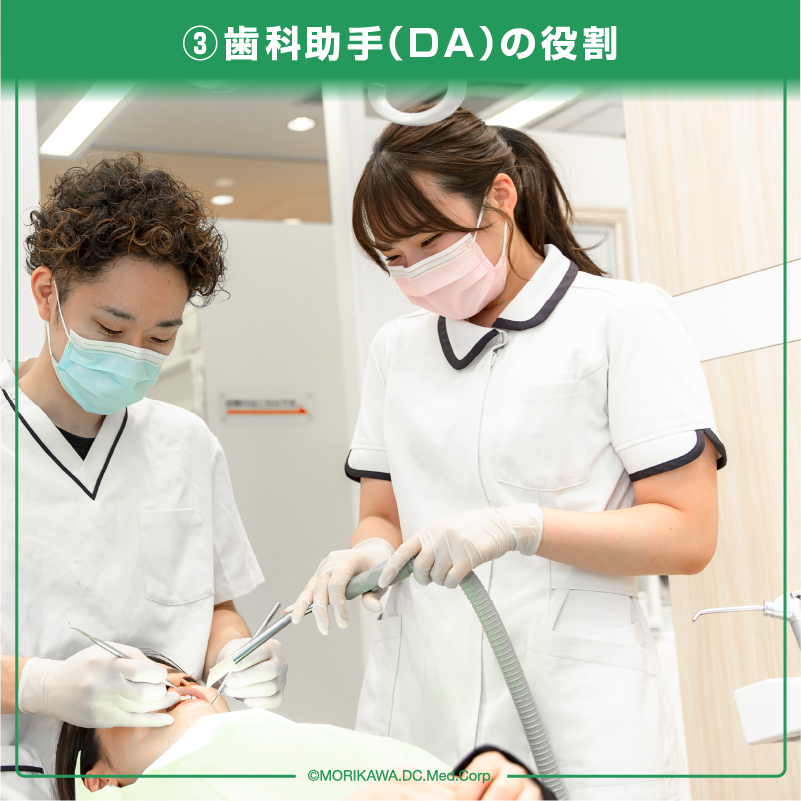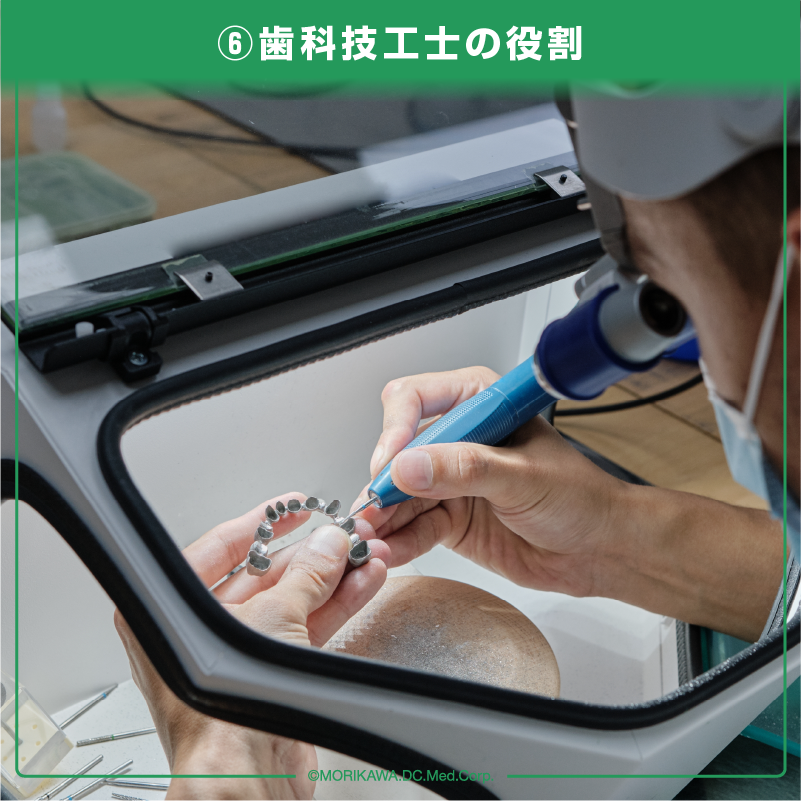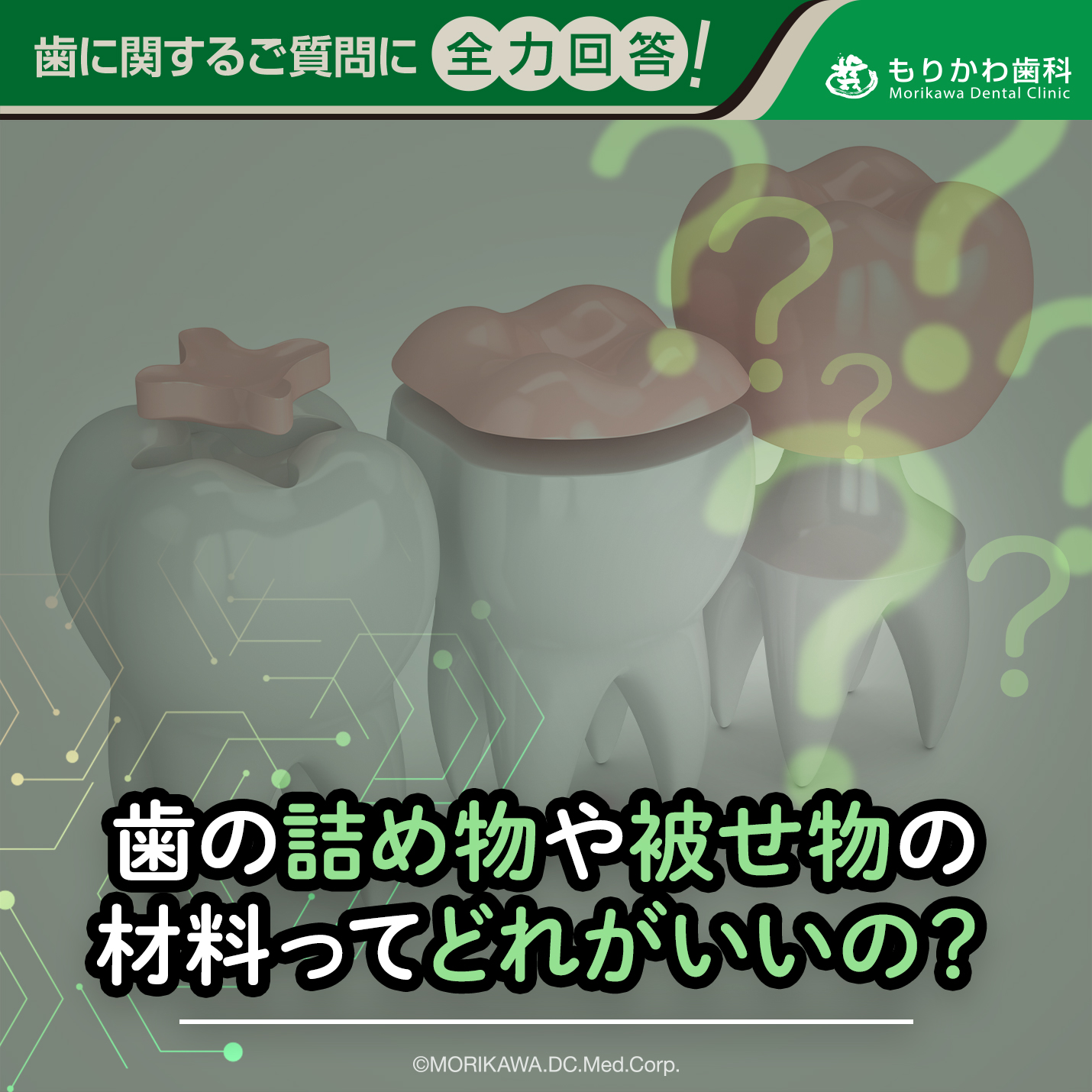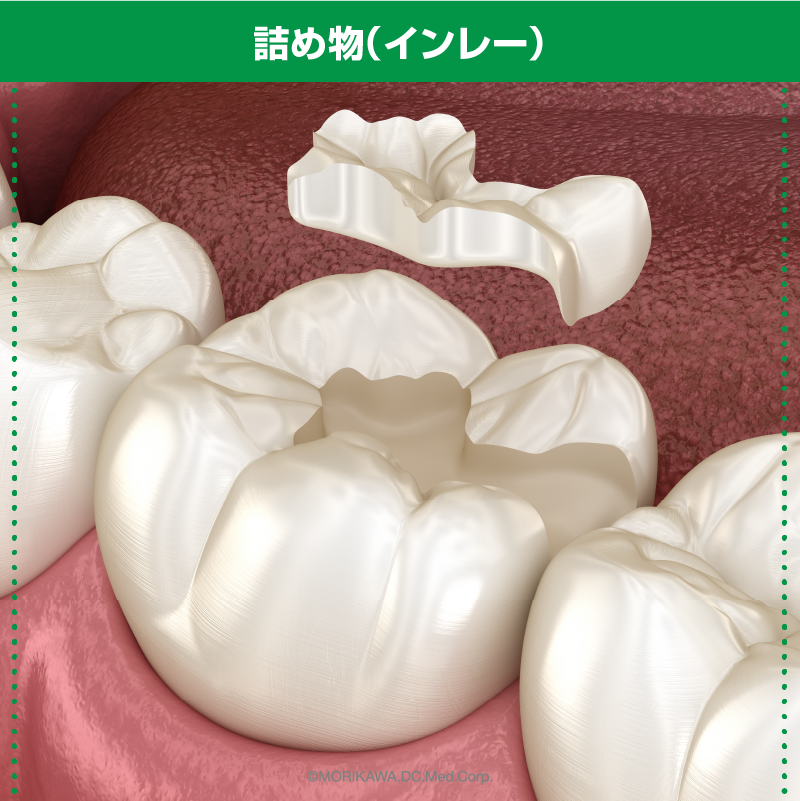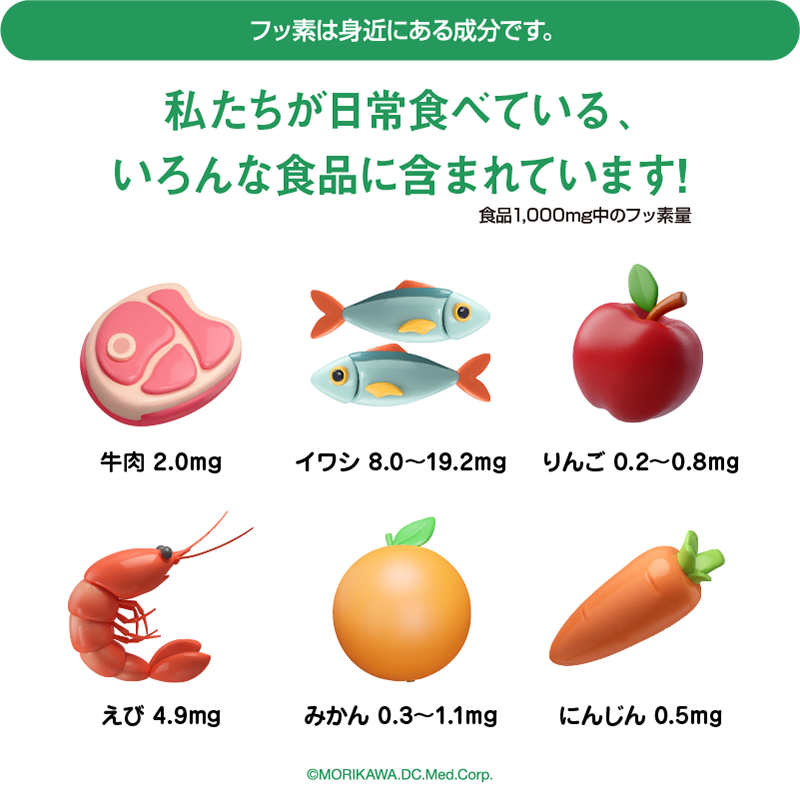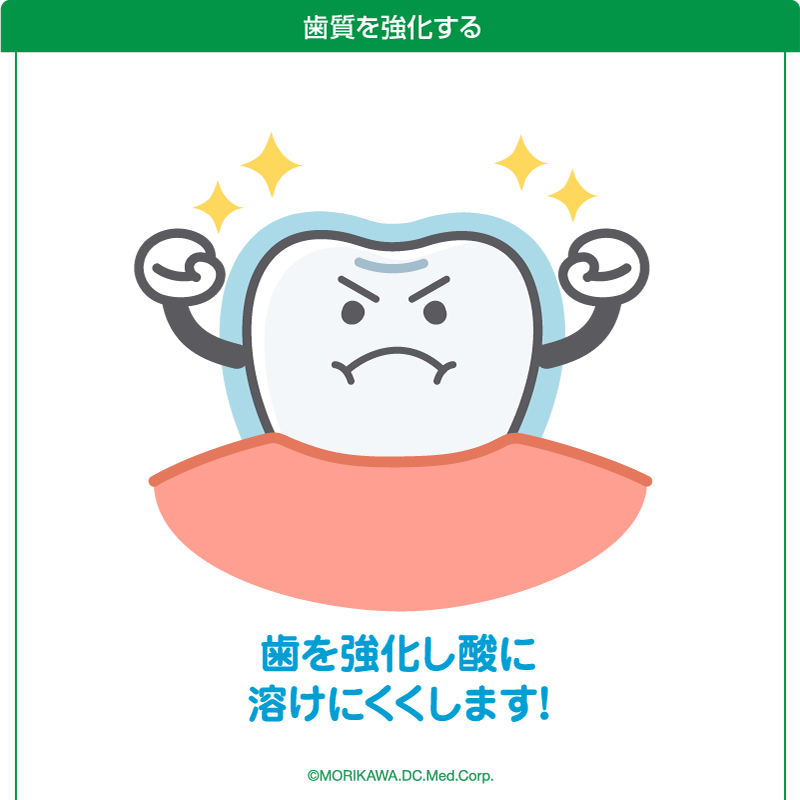こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所です。
歯ぎしりと歯周病は、何も関係がないように思うかもしれません。
しかし、歯ぎしりをすることによって、歯周病が悪化すると考えられています。なぜ、歯ぎしりが歯周病の悪化の原因になるのでしょうか。
本記事では、歯ぎしりと歯周病の関係性について詳しく解説します。また、歯ぎしりは歯周病以外にも様々なトラブルを引き起こすので、他のトラブルや歯ぎしりの対処法などもご紹介します。
歯ぎしりにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
歯周病とは?

歯周病とは、歯周ポケットから侵入した細菌が歯肉に炎症を引き起こし、進行すると歯槽骨を溶かすこともある病気です。
歯肉炎と歯周炎をあわせた状態と定義されており、日本では虫歯と並んで歯科の2大疾患とも呼ばれています。現在、40歳以上の日本人の半数以上が歯周病に罹患しているとされています。
歯周病の原因は歯周病菌で、数十種類以上の歯周病菌が組み合わさって歯周病を発症させています。歯磨きが十分にできていない方や糖尿病の方、歯ぎしりのクセがある方などは、リスクが高いとされています。
歯周病の症状は、進行度で異なります。軽度の歯周病の場合は歯茎が赤く腫れて、触ると出血することがあるでしょう。
軽度の歯周病の段階で、歯周ポケットは2~4mm程度の深さになります。歯周ポケットから細菌が侵入することで症状が進行し、歯茎の腫れや出血に加えて歯周ポケットがさらに深くなります。
中等度の歯周病では、4~6mm程度になるでしょう。重度になると6mmを超えます。
歯周ポケットに歯垢や歯石が蓄積して細菌が繁殖するため、口臭が悪化する方もいます。歯周病が進行すると歯槽骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちることもあるでしょう。
歯ぎしりとは?

歯ぎしり(ブラキシズム)とは、上下の歯が必要なタイミング以外で接触している状態のことを言います。噛んだり会話したりする時以外は、上下の歯は接触していないのが正常なのです。
歯ぎしりの原因には、ストレスや噛み合わせの異常、生活習慣などが挙げられます。特に、ストレスは歯ぎしりの最も大きな原因と考えられています。
歯ぎしりは寝ている時に起こる場合と、目覚めている時に起こる場合で分類されます。
寝ている時に起こる歯ぎしりを睡眠時ブラキシズムと呼びます。無意識に行うため制御ができず、非常に強い力がかかることが特徴です。睡眠中は、歯をぎりぎりと左右に動かすグラインディングという種類の歯ぎしりをすることが多いです。
起きている時に行われる歯ぎしりを、覚醒時ブラキシズムと言います。覚醒時ブラキシズムも無意識で行われることが多いですが意識的に行われる場合もあり、さまざまな種類の歯ぎしりをすることが特徴です。
前述したグラインディングの他に、歯をカチカチと打ち鳴らすタッピングや、ぐっと歯を噛みしめるクレンチングなどの種類があります。
歯ぎしりをすると歯周病が悪化する?

歯ぎしりが歯周病の直接的な原因になっているわけではありませんが、歯に強い負担がかかることにより、歯周病が悪化する可能性があると考えられています。
歯周病で炎症が生じている歯茎に歯ぎしりや食いしばりで強い力がかかると、炎症が激しくなるのです。また、歯肉や歯周組織に大きな負担がかかるため、歯肉が衰えたり特定部分の骨吸収を促進させたりするケースもあるでしょう。
歯肉が衰えている状態で歯周病菌が侵入すると、歯周病が悪化しやすいのです。
歯ぎしりが引き起こすトラブル

歯ぎしりは歯周病の悪化につながるだけでなく、他にもさまざまなトラブルを引き起こします。ここからは、歯ぎしりが引き起こすトラブルについて解説します。
顎関節症
歯ぎしりが引き起こすトラブルとして、代表的なものが顎関節症です。歯ぎしりによって顎に過度な力がかかり続けると、顎の骨や筋肉などにもダメージを与えます。
長期間にわたって顎の関節を構成する骨などに負担をかけ続けた結果、顎関節症が引き起こされると考えられています。
顎関節症の主な症状として、顎の痛みや不快感、口を開け閉めする際に音が鳴ることなどが挙げられます。頭痛や首・肩の痛みなどが引き起こされる場合もあり、日常生活に支障をきたす恐れがあるでしょう。
歯が摩耗・損傷する
歯ぎしりは、歯の摩耗や損傷を引き起こします。歯ぎしりを長期的に行うと、歯がすり減って噛み合わせや歯並びへ悪影響を及ぼすこともあるでしょう。
歯ぎしりをすると、歯の表面にあるエナメル質もすり減ります。エナメル質がすり減って象牙質がむき出しになると、神経に刺激が伝わりやすくなり、知覚過敏を引き起こすかもしれません。冷たいものや熱いものを摂取する際に、しみたり痛みを感じたりすることがあるでしょう。
他にも、歯に詰め物があった場合には詰め物が外れてしまったり壊れたりする他、自身の歯が欠けたり折れたりすることもあります。歯の損傷を防ぐためには、早期の治療やマウスガードでの対策が効果的です。
全身に影響を及ぼす
歯ぎしりは、口腔内だけでなく全身に影響を及ぼすことがあります。歯ぎしりによって強い力を歯や顎にかけ続けていると、顎や首、肩などの筋肉が緊張状態になるため、頭痛や肩凝りの原因になるのです。
顔のバランスが崩れる
歯ぎしりを続けていると、顔の見た目にも影響が出ます。特に、エラ張りと歯ぎしりは密接に関係していると考えられています。
歯ぎしりは、顔のエラと呼ばれる部分にある咬筋を発達させるため、エラが張った顔立ちになる可能性があるのです。「エラの張りを何とかしたい」と考え美容医療を受ける方の中には、歯ぎしりをやめただけで改善するケースもあります。
また、顎のズレやゆがみを引き起こしたり、筋肉が引っ張られることで目の大きさが片方だけ変わったりするなど、顔のバランスが崩れやすくなります。
歯ぎしりの癖がある場合の対処法

歯ぎしりは身体にさまざまな症状を引き起こすリスクがあるため、歯ぎしりの癖がある方は早急に対処し改善しましょう。特に、寝ている間など無意識のうちに歯ぎしりをしている場合には、何らかの対処を行わなければ身体への影響が大きくなります。
ここからは、歯ぎしりの癖がある場合の対処法について解説します。
マウスピースを装着する
「寝ている間に無意識に起こっている歯ぎしりを何とかしたい」という方に有効なのが、マウスピースを装着することです。
就寝時にマウスピースを使用することによって、歯と歯が直接接触するのを防ぎ、咬合力を分散させる役割を果たします。そのため、歯や顎関節にかかる負担を軽減できます。
歯科医院で作製したマウスピースの場合、患者さまに合わせて作られているため、より快適に使用することができるでしょう。
薬物療法
薬を使って歯ぎしりを改善させる方法です。筋弛緩剤などを使用し、筋肉の緊張を軽減させます。
しかし、薬剤の使用は慎重に行わなければなりません。依存症になる可能性があることや副作用があることなどの観点から、長期的には使用できないでしょう。
まとめ

歯ぎしりをすると顎の骨や歯周組織に負担がかかり、歯周病を悪化させる可能性があるとされています。口内の健康を守るためには、歯ぎしりをなるべくしないことが望ましいでしょう。
しかし、寝ている間など無意識に歯ぎしりをしている場合、自身の意識だけでは改善が難しいケースもあります。マウスピースの装着で歯への負担を軽減したり、薬物を使用して歯ぎしりを抑制したりしましょう。
マウスピースは、市販品よりも歯科医院でオーダーメイドで作成してもらったほうが外れにくく、確実な効果が期待できます。
歯ぎしりでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科志紀診療所」にお気軽にご相談ください。